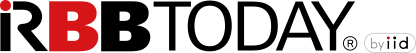※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
【特集・Netflix】第1回 日本上陸!米在住者から見た動画配信サービス「Netflix」とは
2015-06-17 19:06:17
いま、アメリカのストリーミング動画配信プラットフォーム大手のNetflix(ネットフリックス)の日本上陸が大きな話題となっている。Xデーは今秋。50カ国超での展開、世界全体で6200万人(2015年第一四半期実績、内米国が4100万人強)を超える加入者を抱えるまさに世界最大級の動画配信サービスだ。
そのNetflixが、果たして日本にどれだけのインパクトをもたらすのか、あるいはもたらさないのか。アメリカ在住の筆者が自らの体験を交えて分析してみたい。
Netflixは、米国では現在月額7.99ドル(初月無料)で見放題のサービスを提供している。もともとはDVDのレンタルサービスから始まり、レンタルビデオチェーン大手のブロックバスターらを駆逐したが、2007年からストリーミング配信を主要事業に据えた。
この事業転換は株式市場から反感を買い、2011年には株価の急落を招く。しかし、結果的にはケーブルテレビの割高なコンテンツへの反発とブロードバンドへの普及で漁夫の利を得た形でシェアを飛躍的に伸ばしてきた。
ROKUなどのSTBやスマートテレビでNetflixを搭載していないということは考えられないほどの規模であり、Netflixボタンがリモコンに搭載されている機種すらあるほどだ。
DVDが主流だった時に、レンタルビデオよりも、セレクションや価格の点で「顧客に優しい」システムで認知度とシェアを獲得し、ブロードバンドやモバイル端末の普及の兆しを見るや時代の流れを察知し、いち早く方向転換した。その敏感なアンテナと大胆な経営戦略こそが同社の強みである。
■「I love Netflix!」と口をそろえる米の友人たち
例えば、筆者は先日までディズニーにコンサルタントとして関わっていたのだが、ある日、月例で開催されるスタッフの誕生日パーティでネット動画に関する会話が始まった。
よく聞いて驚いたことに、その場にいた10名以上のメンバー全員がNetflixかHuluのどちらかを利用していたのである。彼らの口から “I love Netflix!”というセリフを何度聞いたことか。
また、我が家には上は13歳から下は8歳までに4人の子どもがいるが、同年代か少し下の子どもがいるアメリカ人の父親仲間との会話では、Huluより子ども向けにコンテンツが充実しているNetflixを視聴しているという話をよく聞く。
有料のHulu Plusも月額7.99ドル。いくら安いとはいえ、両方購読している人の話はあまり聞かない。体感的には10人に1人くらいだろうか。Hulu Plusの会員は、2015年現在900万人超と発表されているので、Netflixには水をあけられた格好である。
ネットの影響や若者のライフスタイルの変化によるテレビの凋落ぶりがとかく話題にのぼる日本と異なり、米国では依然テレビがメディアの王道という印象がある。
そしてコンテンツの王様といえば4大スポーツであり、最大の視聴率を集めるのがアメリカンフットボール(NFL)だ。NFLはプライムタイムの他番組の3倍規模の視聴者を獲得するというのだから、そのなかでも最大のイベントである「スーパーボウル」のインパクトは説明するまでもないだろう。
ペイトリオッツ(マサチューセッツ州)対シーホークス(ワシントン州)が接戦を繰り広げた、今年のスーパーボウルの視聴率は50%に届こうかという勢いで、じつに米国在住の1.2億人が観戦したとされる。
広告費用も王様の名にふさわしいもので、30秒で400万ドル(現在のレートで約5億円)だというからすごい。日本では一番人気のプロ野球ですらテレビでの露出がどんどん少なくなってきていると聞くので、大きな違いだ。
■ケーブルテレビの売り上げ不振
だが実は、それでも米国のテレビ業界全体でいうと、広告費用や視聴者数はインターネットにどんどん奪われており、ケーブルテレビ各社は頭を悩ませている状況なのである。
これを牽引しているのがモバイル端末からの視聴だ。売り上げ不振で合併報道が相次ぐケーブルテレビ各社も最近では、モバイル端末から虎の子のスポーツコンテンツを視聴してもらうべく環境整備を充実させてきているし、ソーシャルメディアやセカンドスクリーン対策にも余念がない。
テレビ業界はスポンサーで成り立っているから、視聴者数を維持しないことには話にならない。しかし、視聴者の選択肢が拡大するにつれ、無料のオプションも増えてくる。
これはリビングルーム中心の視聴文化がより多様化していることを示しており、場所(モバイル化)と時間(タイムシフト)を選ばない視聴スタイルがより好まれるようになってきているのは間違いない。
アメリカで話題になっている「コード・カッティング」は、割高なケーブルテレビのコンテンツ購読を解約して、インターネットを中心としたよりリーゾナブル(あるいは無料)の動画視聴に重点を置くというトレンドである。
もっとも先に述べたスポーツは生放送の視聴が中心だ。日本でもNHKが受信料の徴収対象をインターネットや携帯端末にまで拡げる意図があるということで大きな議論を呼んでいるが、アメリカのケーブルテレビは、NHKの受信料よりかなり割高で、大概インターネット・プロバイダや電話などと合わせたパッケージ契約になってくる。
■Netflixは現代の追い風を受けて発展した“時代の寵児”
先日コムキャストとの大型合併が当局に認められず、新たに業界第5位のCharterから553億ドルという巨額の買収話が持ち上がっている業界第2位のタイム・ワーナー・ケーブル(TWC)と、我が家は契約をしている。毎月145ドル(18,800円)もするコストを何とか節約して家計を良くするために(笑)、契約更新の度にコード・カッティングに挑戦するのだが、成功した試しがない。
そもそも高価なプレミアム・チャンネルを省いたベーシック契約しかないため、コストを下げようとすれば、ケーブルテレビを解約して無料の地デジに切り替えるくらいだが、日本と比べると遥かに遅いとはいえ、最近ではかなり速くなった(といっても実速16Mbps程度)。
ブロードバンド回線は気に入っているので、それだけは残したい。しかし、それを元に新たな価格を提示してもらうと、何故か逆に高くなると言われるから不思議である。交渉も功を奏さず、理不尽な料金体系にいつも狐につままれたような感じで電話を切るのだが、同じ経験をした人は多いはずである。それくらいケーブルテレビ各社は、「カット」されないように、あの手この手で努力しており、皮肉なことにインターネットがその最後の砦となっているのだ。
Netflixは、テレビとインターネットの融合という時代の追い風を存分に受けて隆盛した時代の寵児である。インターネットの動画視聴といえば、もちろん世界最大のYouTubeだが、DVD全盛の視聴スタイルからより便利なストリーミングやダウンロードでテレビや映画のコンテンツを合法的に見るためにはNetflixやHuluを利用する必要があった。
■NetflixやHuluが生き残った一方で……
モバイル全盛になる前にアメリカでこれらの導入の牽引役を担ったのが、ROKUに代表されるセットトップボックス(STB)で、これによりようやくインターネットと当時流行し出した40インチ以上の大画面液晶テレビが繋がることになる。
Apple TVは我が家でも愛用しており、iPhoneのコンテンツを大画面で視聴できるAirPlayは非常に便利だが、GoogleのChromecastと合わせてもROKUの利用者が圧倒的に多い気がする。そして実に2,000以上のチャンネルと25万タイトル以上のコンテンツを誇るというROKUのキラーコンテンツといえばやはりNetflixだ。
ネットビジネスでは1位しか生き残れないと言われるように、NetflixとHuluが独自の地位を獲得するまでに駆逐された同業サービスは後を絶たない。VemeoはYouTubeに完全敗北。JOOSTはコンテンツで負けて見る影もなくなり、2012年に事実上操業停止。VEOHも“ウリ”だった違法コンテンツに足を引っ張られ、2010年に廃業を余儀なくされた。
実際テレビとインターネットの親和性は非常に高く、市場からは絶大な支持を得ている。『メディアユニバース調査 2014年版』(ニールセン)によると、いまでは米国内の世帯のほとんどがHDTVやインターネットに接続されたコンピュータやスマートフォンを保有しており、週の視聴時間は実に60時間にも及ぶという。
日本と同様にDVR機器によるタイムシフト録画やストリーミング配信専用のコンテンツの普及などにより、視聴時間や方法の選択肢の幅はどんどん広がっており、視聴者のニーズにきめ細やかに対応できる環境が整いつつある。ニールセンによると、タイムシフト視聴の利用者は1.1億人で2010年以来、毎年二桁伸長を続けているのだそうだ。
■人気チャンネルを持つViacomのリストラ騒動
今年大きな話題になったのが、「スポンジ・ボブ」などで有名なニコロデオンなどの子ども向けチャンネルや、MTVなどのエンタメ系コンテンツなどの人気チャンネルを抱えるメディア大手Viacom(バイアコム)のリストラ騒動で、その経済効果は7.85億ドル(1000億円)にも及ぶと言われる。これにより400名のスタッフも解雇される見通しと伝えられた。
それもそのはず、同ネットワークが有する若者向けのチャンネルのニコロデオン(-34%)、コメディ・セントラル(-30%)、スパイク(-23%)、そしてMTV(-34%)が軒並み売上を減らしているのだ。
これは間違いなくネットの影響であるというのは、広告市場におけるモバイル広告の著しい出稿増加やネット接続されたテレビの数により裏付けられるだろう。実は、筆者の友人の友人がバイアコム系列でエグゼクティブとして働いており、この人事に伴いグループの他の会社の役員になったそうだと、同社の内情を明かしてくれた。
では最後に、話を日本に戻したい。アメリカからのネット動画配信サービスといえば、Huluの日本進出(2011年)が記憶に新しい。筆者も当時、単身赴任先の東京でアメリカの人気テレビ番組「プリズン・ブレイク」を全シリーズ観たのだが、独自の字幕翻訳の品質もなかなかの上出来なうえ、スマホからの視聴体験もストレスなく大変楽しませてもらった。
その後、Huluは昨年春、日本テレビに買収されたが、これは筆者にとっては意外だった。アメリカであれだけ勢いのあるニューメディアのHuluが日本では既存メディアの軍門に下ったようにしか見えなかったからだ。
こうした過去の先達を見た時、Netflixにとっていくつかの課題が浮かび上がってくる。このタイミングで日本進出するものの、勝機はどれくらいあるのだろうか。日本とアメリカを往復することの多い筆者からすると、日米のテレビ文化には、いくつかの乖離があるような気がしている。次回コラムでは、それらを4つのポイントに分けながら、Netflixの日本展開を占ってみたい。
筆者:立入勝義(たちいり・かつよし)
LA在住のブロガー、ソーシャルメディアプロデューサー。著書に「ソーシャルメディア革命」や「電子出版の未来図」など。ブログ「意力(いちから)」管理人
そのNetflixが、果たして日本にどれだけのインパクトをもたらすのか、あるいはもたらさないのか。アメリカ在住の筆者が自らの体験を交えて分析してみたい。
Netflixは、米国では現在月額7.99ドル(初月無料)で見放題のサービスを提供している。もともとはDVDのレンタルサービスから始まり、レンタルビデオチェーン大手のブロックバスターらを駆逐したが、2007年からストリーミング配信を主要事業に据えた。
この事業転換は株式市場から反感を買い、2011年には株価の急落を招く。しかし、結果的にはケーブルテレビの割高なコンテンツへの反発とブロードバンドへの普及で漁夫の利を得た形でシェアを飛躍的に伸ばしてきた。
ROKUなどのSTBやスマートテレビでNetflixを搭載していないということは考えられないほどの規模であり、Netflixボタンがリモコンに搭載されている機種すらあるほどだ。
DVDが主流だった時に、レンタルビデオよりも、セレクションや価格の点で「顧客に優しい」システムで認知度とシェアを獲得し、ブロードバンドやモバイル端末の普及の兆しを見るや時代の流れを察知し、いち早く方向転換した。その敏感なアンテナと大胆な経営戦略こそが同社の強みである。
■「I love Netflix!」と口をそろえる米の友人たち
例えば、筆者は先日までディズニーにコンサルタントとして関わっていたのだが、ある日、月例で開催されるスタッフの誕生日パーティでネット動画に関する会話が始まった。
よく聞いて驚いたことに、その場にいた10名以上のメンバー全員がNetflixかHuluのどちらかを利用していたのである。彼らの口から “I love Netflix!”というセリフを何度聞いたことか。
また、我が家には上は13歳から下は8歳までに4人の子どもがいるが、同年代か少し下の子どもがいるアメリカ人の父親仲間との会話では、Huluより子ども向けにコンテンツが充実しているNetflixを視聴しているという話をよく聞く。
有料のHulu Plusも月額7.99ドル。いくら安いとはいえ、両方購読している人の話はあまり聞かない。体感的には10人に1人くらいだろうか。Hulu Plusの会員は、2015年現在900万人超と発表されているので、Netflixには水をあけられた格好である。
ネットの影響や若者のライフスタイルの変化によるテレビの凋落ぶりがとかく話題にのぼる日本と異なり、米国では依然テレビがメディアの王道という印象がある。
そしてコンテンツの王様といえば4大スポーツであり、最大の視聴率を集めるのがアメリカンフットボール(NFL)だ。NFLはプライムタイムの他番組の3倍規模の視聴者を獲得するというのだから、そのなかでも最大のイベントである「スーパーボウル」のインパクトは説明するまでもないだろう。
ペイトリオッツ(マサチューセッツ州)対シーホークス(ワシントン州)が接戦を繰り広げた、今年のスーパーボウルの視聴率は50%に届こうかという勢いで、じつに米国在住の1.2億人が観戦したとされる。
広告費用も王様の名にふさわしいもので、30秒で400万ドル(現在のレートで約5億円)だというからすごい。日本では一番人気のプロ野球ですらテレビでの露出がどんどん少なくなってきていると聞くので、大きな違いだ。
■ケーブルテレビの売り上げ不振
だが実は、それでも米国のテレビ業界全体でいうと、広告費用や視聴者数はインターネットにどんどん奪われており、ケーブルテレビ各社は頭を悩ませている状況なのである。
これを牽引しているのがモバイル端末からの視聴だ。売り上げ不振で合併報道が相次ぐケーブルテレビ各社も最近では、モバイル端末から虎の子のスポーツコンテンツを視聴してもらうべく環境整備を充実させてきているし、ソーシャルメディアやセカンドスクリーン対策にも余念がない。
テレビ業界はスポンサーで成り立っているから、視聴者数を維持しないことには話にならない。しかし、視聴者の選択肢が拡大するにつれ、無料のオプションも増えてくる。
これはリビングルーム中心の視聴文化がより多様化していることを示しており、場所(モバイル化)と時間(タイムシフト)を選ばない視聴スタイルがより好まれるようになってきているのは間違いない。
アメリカで話題になっている「コード・カッティング」は、割高なケーブルテレビのコンテンツ購読を解約して、インターネットを中心としたよりリーゾナブル(あるいは無料)の動画視聴に重点を置くというトレンドである。
もっとも先に述べたスポーツは生放送の視聴が中心だ。日本でもNHKが受信料の徴収対象をインターネットや携帯端末にまで拡げる意図があるということで大きな議論を呼んでいるが、アメリカのケーブルテレビは、NHKの受信料よりかなり割高で、大概インターネット・プロバイダや電話などと合わせたパッケージ契約になってくる。
■Netflixは現代の追い風を受けて発展した“時代の寵児”
先日コムキャストとの大型合併が当局に認められず、新たに業界第5位のCharterから553億ドルという巨額の買収話が持ち上がっている業界第2位のタイム・ワーナー・ケーブル(TWC)と、我が家は契約をしている。毎月145ドル(18,800円)もするコストを何とか節約して家計を良くするために(笑)、契約更新の度にコード・カッティングに挑戦するのだが、成功した試しがない。
そもそも高価なプレミアム・チャンネルを省いたベーシック契約しかないため、コストを下げようとすれば、ケーブルテレビを解約して無料の地デジに切り替えるくらいだが、日本と比べると遥かに遅いとはいえ、最近ではかなり速くなった(といっても実速16Mbps程度)。
ブロードバンド回線は気に入っているので、それだけは残したい。しかし、それを元に新たな価格を提示してもらうと、何故か逆に高くなると言われるから不思議である。交渉も功を奏さず、理不尽な料金体系にいつも狐につままれたような感じで電話を切るのだが、同じ経験をした人は多いはずである。それくらいケーブルテレビ各社は、「カット」されないように、あの手この手で努力しており、皮肉なことにインターネットがその最後の砦となっているのだ。
Netflixは、テレビとインターネットの融合という時代の追い風を存分に受けて隆盛した時代の寵児である。インターネットの動画視聴といえば、もちろん世界最大のYouTubeだが、DVD全盛の視聴スタイルからより便利なストリーミングやダウンロードでテレビや映画のコンテンツを合法的に見るためにはNetflixやHuluを利用する必要があった。
■NetflixやHuluが生き残った一方で……
モバイル全盛になる前にアメリカでこれらの導入の牽引役を担ったのが、ROKUに代表されるセットトップボックス(STB)で、これによりようやくインターネットと当時流行し出した40インチ以上の大画面液晶テレビが繋がることになる。
Apple TVは我が家でも愛用しており、iPhoneのコンテンツを大画面で視聴できるAirPlayは非常に便利だが、GoogleのChromecastと合わせてもROKUの利用者が圧倒的に多い気がする。そして実に2,000以上のチャンネルと25万タイトル以上のコンテンツを誇るというROKUのキラーコンテンツといえばやはりNetflixだ。
ネットビジネスでは1位しか生き残れないと言われるように、NetflixとHuluが独自の地位を獲得するまでに駆逐された同業サービスは後を絶たない。VemeoはYouTubeに完全敗北。JOOSTはコンテンツで負けて見る影もなくなり、2012年に事実上操業停止。VEOHも“ウリ”だった違法コンテンツに足を引っ張られ、2010年に廃業を余儀なくされた。
実際テレビとインターネットの親和性は非常に高く、市場からは絶大な支持を得ている。『メディアユニバース調査 2014年版』(ニールセン)によると、いまでは米国内の世帯のほとんどがHDTVやインターネットに接続されたコンピュータやスマートフォンを保有しており、週の視聴時間は実に60時間にも及ぶという。
日本と同様にDVR機器によるタイムシフト録画やストリーミング配信専用のコンテンツの普及などにより、視聴時間や方法の選択肢の幅はどんどん広がっており、視聴者のニーズにきめ細やかに対応できる環境が整いつつある。ニールセンによると、タイムシフト視聴の利用者は1.1億人で2010年以来、毎年二桁伸長を続けているのだそうだ。
■人気チャンネルを持つViacomのリストラ騒動
今年大きな話題になったのが、「スポンジ・ボブ」などで有名なニコロデオンなどの子ども向けチャンネルや、MTVなどのエンタメ系コンテンツなどの人気チャンネルを抱えるメディア大手Viacom(バイアコム)のリストラ騒動で、その経済効果は7.85億ドル(1000億円)にも及ぶと言われる。これにより400名のスタッフも解雇される見通しと伝えられた。
それもそのはず、同ネットワークが有する若者向けのチャンネルのニコロデオン(-34%)、コメディ・セントラル(-30%)、スパイク(-23%)、そしてMTV(-34%)が軒並み売上を減らしているのだ。
これは間違いなくネットの影響であるというのは、広告市場におけるモバイル広告の著しい出稿増加やネット接続されたテレビの数により裏付けられるだろう。実は、筆者の友人の友人がバイアコム系列でエグゼクティブとして働いており、この人事に伴いグループの他の会社の役員になったそうだと、同社の内情を明かしてくれた。
では最後に、話を日本に戻したい。アメリカからのネット動画配信サービスといえば、Huluの日本進出(2011年)が記憶に新しい。筆者も当時、単身赴任先の東京でアメリカの人気テレビ番組「プリズン・ブレイク」を全シリーズ観たのだが、独自の字幕翻訳の品質もなかなかの上出来なうえ、スマホからの視聴体験もストレスなく大変楽しませてもらった。
その後、Huluは昨年春、日本テレビに買収されたが、これは筆者にとっては意外だった。アメリカであれだけ勢いのあるニューメディアのHuluが日本では既存メディアの軍門に下ったようにしか見えなかったからだ。
こうした過去の先達を見た時、Netflixにとっていくつかの課題が浮かび上がってくる。このタイミングで日本進出するものの、勝機はどれくらいあるのだろうか。日本とアメリカを往復することの多い筆者からすると、日米のテレビ文化には、いくつかの乖離があるような気がしている。次回コラムでは、それらを4つのポイントに分けながら、Netflixの日本展開を占ってみたい。
筆者:立入勝義(たちいり・かつよし)
LA在住のブロガー、ソーシャルメディアプロデューサー。著書に「ソーシャルメディア革命」や「電子出版の未来図」など。ブログ「意力(いちから)」管理人
立入勝義
News 特集
MM総研は9日、2015年における携帯電話(フィーチャーフォンとスマートフォン)端末の国内出荷台数に関する調査結果を発表した。総出荷台数は前年比6.6%減の3,577万台。2012年から3年連続で減少が続いている。 [...]
全て見る
Trucks 特集
MM総研は9日、2015年における携帯電話(フィーチャーフォンとスマートフォン)端末の国内出荷台数に関する調査結果を発表した。総出荷台数は前年比6.6%減の3,577万台。2012年から3年連続で減少が続いている。 [...]
全て見る
Equipments 特集
Amazon.co.jp(アマゾン)は4日、「Amazonお酒ストア」内の「Amazonワインストア」において、 専門家がワインを選んでくれる新サービス「Amazonソムリエ」の提供を開始した。 [...]
全て見る