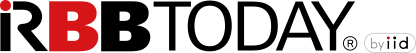※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
【特集・Netflix】第2回 黒船の日本展開でカギを握る4つのポイント
2015-06-18 06:00:04
いよいよ日本上陸が今秋に迫る、アメリカのストリーミング動画配信プラットフォーム大手のNetflix(ネットフリックス)。50カ国超で展開し、世界全体で6200万人を超える加入者を抱えている、この世界最大級の動画配信サービスにいま注目が集まっている。
前回のコラムでは、アメリカに在住している筆者の実体験を交えながら、アメリカにおけるNetflixの実態について解説したが、今回は、同社が日本で展開するうえで重要となるであろう4つのポイントを整理してみたい。
■1.コンテンツ
デヴィッド・フィンチャーの制作総指揮、そしてケヴィン・スペイシー主演で話題となった『ハウス・オブ・カード 野望の階段』に代表されるオリジナルコンテンツを盛んに制作して市場に刺激を与えているNetflix。そうした同社のコンテンツに大きな関心を寄せている日本人ファンも多いだろう。個人的にはこれは翻訳の質如何に関わってくることが多いような気もするのだが、どのレベルで出してくるのかが見ものだ。
それに加えて「日本の皆さんに低額の世界的エンタメコンテンツを提供するだけでなく、日本の人気映画やテレビ番組を世界5,700万人のNetflixユーザーに提供していく」というNetflix日本法人代表グレゴリー・ピーターズ氏のコメント(2015年2月の同社プレスリリース)は、日本のコンテンツ制作者にも強い期待を抱かせているはずだ。
実に3.2億部という堂々たる発行部数で単一作者によるマンガ発行部数世界一の作品と認定された『ONE PIECE』や『NARUTO』は、世界的にファンが多い作品として知られており、動画も大人気だ。
昨年夏には、米国でもディズニーのアニメネットワークの一つである、ディズニーXDが遂に日本の長寿人気コンテンツ「ドラえもん」の配信権を獲得して、若干のローカライズを含め話題になったが、まだまだ日本のアニメは世界のテレビネットワークでみるとニッチ的な存在であることは否めない。
そんなテレビを通り越し、Netflixの勢いを借りて一気にマスにアピールする作品が今後登場していくのか、あるいは予想外のタイトルが人気になったりするのか。日本の製作者が、世界に向けてオリジナルコンテンツを出していくような新たな市場の登場に期待したい。
■2.媒体別の視聴体験
先日の日本出張時、家電量販店では米国よりも多く4Kテレビが販売されているのを見かけた。Netflixが鳴り物入りで日本市場に入って独立的な立場で、市場の起爆剤となる可能性には、テレビのメーカーも期待を寄せているかもしれない。
4Kテレビはアメリカでも徐々に普及してきており、昨年と今年の 「CES」(ラスベガスで開催される世界最大の家電ショー)でも目玉の一つになっていたが、アメリカではテレビよりもネットが先行するのではないかと言われている。
4Kテレビの価格は、当初の1インチ100ドル(約13,000円)を今では大きく下回ってきていて、比較的求めやすくはなってきたものの、視聴環境が整っておらず、NetflixのUltra HD視聴は4Kテレビ所持者から熱い視線を浴びている(Ultra HD視聴にはプレミアム契約が必要で月額料金は11.99ドル)。
Netflixでの主流コンテンツがテレビ番組になるのか、映画になるのかはわからない。洋楽が売れなくなって久しいが、実際に洋画の方も邦画全体の興行収益が洋画のそれを上回る「邦高洋低」傾向が2012年から続いているとされる。
ディズニーの「アナと雪の女王」のような例外的な大ヒットコンテンツを除けば、洋画離れが進む日本で海外タイトルの需要がそれほどあるのだろうか。
ベンチマークとなりそうなHuluは、今年3月にようやく100万人突破となったが、採算ラインに乗せるためにはもっと大きな数字を、3年以内などの早いタイミングで達成する必要があるのではないか。
特にモバイル視聴を好む若い世代にささるコンテンツと視聴体験を供給できるかについては格段の配慮が必要とされるだろう。モバイルだけでなく、HuluがPlaystation 4にも対応したように、ゲームコンソールへの対応も求められそうに思う。
また日本とアメリカを比較するとスマートテレビ関連でも大きな違いが出ている。
実際、まだまだスマートテレビが立ち上がっているという状態ではないが、ROKU以外にもクロームキャストやApple TVなど選択肢が着実に普及しているアメリカとは異なり、日本ではHD搭載テレビの性能がよくスマートに録画して楽しむ傾向がある。
今年から始まった「タイムシフト視聴率」のようなKPIを何らかの形でNetflixも提供することはできたら面白そうなのだが。
■3.同業者との競合、メディア戦略
日本の同業者との競合事情はどうだろうか。ロサンゼルスで映画関係に従事し、いま日本で某映画館の支配人をしながら映像関係の仕事を続けている杉本穂高氏の意見を尋ねてみた。
「Huluは海外コンテンツ中心で、うまく会員数を伸ばせなかったところに日テレの買収で日本のテレビのコンテンツをたくさん獲得でき、テレビCMという『リーチ力』も手伝ってようやく会員数を伸ばすことができました。流行りのソーシャルゲームやSNSに対する影響を見ても日本ではテレビCMの影響力がまだまだ強いので、リーチ力もコンテンツも最も多く有しているテレビをどう活用するか。また、米国でNetflixは先駆者でしたけれど、日本では後発組ですので、すでにある競合との違いをどう出して見せるのかは、大きな課題でしょう」(杉本氏)
■4.課金モデル
最後に課金モデルである。Hulu Plusは、日本では単なるHuluとしてアメリカより少し高めの値段設定で開始して、現在は月額933円(税抜、2週間無料)、コンテンツ数は1万本。NTTドコモ運営のdTVは、12万タイトルを複数デバイスで楽しむことができる。
日本進出に向けて、どのような課金体制で望むのかについてはかなりシリアスな検討が必要であろう。従来のままで成り立つのか。そして、現在は独自コンテンツのトレーラーにしか掲載されていない広告が他の形で登場することはあり得るのか。
アメリカはITサービスの本丸で、最近のソーシャルメディアの隆盛なども全てアメリカ発だが、実はインターネットビジネス全体を見るとアメリカで普及したサービスが日本でそのまま成立するケースというのは極めて稀である。
最大の失敗事例はeBayだと思うが、PayPalにしても日本の金融事情に阻まれる格好(いまだに日本の銀行口座から入金できないのはなんとかならないものか)で大きな普及はしていない。Twitterは競合がいないため伸長したが、InstagramやPinterestは大きく普及しているとは言い難い。
Facebookは強敵mixiの隙を突いて急成長したが、ZyngaやCandy Crushなどのソーシャルゲームに関しては米国の勢いからするとまったく対応できていない。
言語面もさることながら日本文化に適したきめ細やかな対応、そして何よりスマホブームに乗り急成長したLINEのように時流をつかむというのが非常に大事なのは各国に共通した事情だ。だが、果たして、いまというタイミングがアメリカの動画配信王者Netflixにとって吉と出るか凶と出るのか。
それは現状ではわからないが、一つ言えることは、少なくとも2、3年は本気でリソースを投入していく覚悟がないと成功には至らないということだろう。
これまで時代の流れを読みきって大勝利を収めてきた同社の経営陣が「ガラパゴス」市場として知られる日本の事情と時流を正しく読みきって舵を切れるのだろうか。
オリジナルコンテンツと4Kテレビへの普及が追い風になることを筆者は期待しているし、独自の日本コンテンツが海外で大成功になるような日がきたらと思うとワクワクしてしまう。
筆者:立入勝義(たちいり・かつよし)
LA在住のブロガー、ソーシャルメディアプロデューサー。著書に「ソーシャルメディア革命」や「電子出版の未来図」など。ブログ「意力(いちから)」管理人
前回のコラムでは、アメリカに在住している筆者の実体験を交えながら、アメリカにおけるNetflixの実態について解説したが、今回は、同社が日本で展開するうえで重要となるであろう4つのポイントを整理してみたい。
■1.コンテンツ
デヴィッド・フィンチャーの制作総指揮、そしてケヴィン・スペイシー主演で話題となった『ハウス・オブ・カード 野望の階段』に代表されるオリジナルコンテンツを盛んに制作して市場に刺激を与えているNetflix。そうした同社のコンテンツに大きな関心を寄せている日本人ファンも多いだろう。個人的にはこれは翻訳の質如何に関わってくることが多いような気もするのだが、どのレベルで出してくるのかが見ものだ。
それに加えて「日本の皆さんに低額の世界的エンタメコンテンツを提供するだけでなく、日本の人気映画やテレビ番組を世界5,700万人のNetflixユーザーに提供していく」というNetflix日本法人代表グレゴリー・ピーターズ氏のコメント(2015年2月の同社プレスリリース)は、日本のコンテンツ制作者にも強い期待を抱かせているはずだ。
実に3.2億部という堂々たる発行部数で単一作者によるマンガ発行部数世界一の作品と認定された『ONE PIECE』や『NARUTO』は、世界的にファンが多い作品として知られており、動画も大人気だ。
昨年夏には、米国でもディズニーのアニメネットワークの一つである、ディズニーXDが遂に日本の長寿人気コンテンツ「ドラえもん」の配信権を獲得して、若干のローカライズを含め話題になったが、まだまだ日本のアニメは世界のテレビネットワークでみるとニッチ的な存在であることは否めない。
そんなテレビを通り越し、Netflixの勢いを借りて一気にマスにアピールする作品が今後登場していくのか、あるいは予想外のタイトルが人気になったりするのか。日本の製作者が、世界に向けてオリジナルコンテンツを出していくような新たな市場の登場に期待したい。
■2.媒体別の視聴体験
先日の日本出張時、家電量販店では米国よりも多く4Kテレビが販売されているのを見かけた。Netflixが鳴り物入りで日本市場に入って独立的な立場で、市場の起爆剤となる可能性には、テレビのメーカーも期待を寄せているかもしれない。
4Kテレビはアメリカでも徐々に普及してきており、昨年と今年の 「CES」(ラスベガスで開催される世界最大の家電ショー)でも目玉の一つになっていたが、アメリカではテレビよりもネットが先行するのではないかと言われている。
4Kテレビの価格は、当初の1インチ100ドル(約13,000円)を今では大きく下回ってきていて、比較的求めやすくはなってきたものの、視聴環境が整っておらず、NetflixのUltra HD視聴は4Kテレビ所持者から熱い視線を浴びている(Ultra HD視聴にはプレミアム契約が必要で月額料金は11.99ドル)。
Netflixでの主流コンテンツがテレビ番組になるのか、映画になるのかはわからない。洋楽が売れなくなって久しいが、実際に洋画の方も邦画全体の興行収益が洋画のそれを上回る「邦高洋低」傾向が2012年から続いているとされる。
ディズニーの「アナと雪の女王」のような例外的な大ヒットコンテンツを除けば、洋画離れが進む日本で海外タイトルの需要がそれほどあるのだろうか。
ベンチマークとなりそうなHuluは、今年3月にようやく100万人突破となったが、採算ラインに乗せるためにはもっと大きな数字を、3年以内などの早いタイミングで達成する必要があるのではないか。
特にモバイル視聴を好む若い世代にささるコンテンツと視聴体験を供給できるかについては格段の配慮が必要とされるだろう。モバイルだけでなく、HuluがPlaystation 4にも対応したように、ゲームコンソールへの対応も求められそうに思う。
また日本とアメリカを比較するとスマートテレビ関連でも大きな違いが出ている。
実際、まだまだスマートテレビが立ち上がっているという状態ではないが、ROKU以外にもクロームキャストやApple TVなど選択肢が着実に普及しているアメリカとは異なり、日本ではHD搭載テレビの性能がよくスマートに録画して楽しむ傾向がある。
今年から始まった「タイムシフト視聴率」のようなKPIを何らかの形でNetflixも提供することはできたら面白そうなのだが。
■3.同業者との競合、メディア戦略
日本の同業者との競合事情はどうだろうか。ロサンゼルスで映画関係に従事し、いま日本で某映画館の支配人をしながら映像関係の仕事を続けている杉本穂高氏の意見を尋ねてみた。
「Huluは海外コンテンツ中心で、うまく会員数を伸ばせなかったところに日テレの買収で日本のテレビのコンテンツをたくさん獲得でき、テレビCMという『リーチ力』も手伝ってようやく会員数を伸ばすことができました。流行りのソーシャルゲームやSNSに対する影響を見ても日本ではテレビCMの影響力がまだまだ強いので、リーチ力もコンテンツも最も多く有しているテレビをどう活用するか。また、米国でNetflixは先駆者でしたけれど、日本では後発組ですので、すでにある競合との違いをどう出して見せるのかは、大きな課題でしょう」(杉本氏)
■4.課金モデル
最後に課金モデルである。Hulu Plusは、日本では単なるHuluとしてアメリカより少し高めの値段設定で開始して、現在は月額933円(税抜、2週間無料)、コンテンツ数は1万本。NTTドコモ運営のdTVは、12万タイトルを複数デバイスで楽しむことができる。
日本進出に向けて、どのような課金体制で望むのかについてはかなりシリアスな検討が必要であろう。従来のままで成り立つのか。そして、現在は独自コンテンツのトレーラーにしか掲載されていない広告が他の形で登場することはあり得るのか。
アメリカはITサービスの本丸で、最近のソーシャルメディアの隆盛なども全てアメリカ発だが、実はインターネットビジネス全体を見るとアメリカで普及したサービスが日本でそのまま成立するケースというのは極めて稀である。
最大の失敗事例はeBayだと思うが、PayPalにしても日本の金融事情に阻まれる格好(いまだに日本の銀行口座から入金できないのはなんとかならないものか)で大きな普及はしていない。Twitterは競合がいないため伸長したが、InstagramやPinterestは大きく普及しているとは言い難い。
Facebookは強敵mixiの隙を突いて急成長したが、ZyngaやCandy Crushなどのソーシャルゲームに関しては米国の勢いからするとまったく対応できていない。
言語面もさることながら日本文化に適したきめ細やかな対応、そして何よりスマホブームに乗り急成長したLINEのように時流をつかむというのが非常に大事なのは各国に共通した事情だ。だが、果たして、いまというタイミングがアメリカの動画配信王者Netflixにとって吉と出るか凶と出るのか。
それは現状ではわからないが、一つ言えることは、少なくとも2、3年は本気でリソースを投入していく覚悟がないと成功には至らないということだろう。
これまで時代の流れを読みきって大勝利を収めてきた同社の経営陣が「ガラパゴス」市場として知られる日本の事情と時流を正しく読みきって舵を切れるのだろうか。
オリジナルコンテンツと4Kテレビへの普及が追い風になることを筆者は期待しているし、独自の日本コンテンツが海外で大成功になるような日がきたらと思うとワクワクしてしまう。
筆者:立入勝義(たちいり・かつよし)
LA在住のブロガー、ソーシャルメディアプロデューサー。著書に「ソーシャルメディア革命」や「電子出版の未来図」など。ブログ「意力(いちから)」管理人
立入勝義
News 特集
MM総研は9日、2015年における携帯電話(フィーチャーフォンとスマートフォン)端末の国内出荷台数に関する調査結果を発表した。総出荷台数は前年比6.6%減の3,577万台。2012年から3年連続で減少が続いている。 [...]
全て見る
Trucks 特集
MM総研は9日、2015年における携帯電話(フィーチャーフォンとスマートフォン)端末の国内出荷台数に関する調査結果を発表した。総出荷台数は前年比6.6%減の3,577万台。2012年から3年連続で減少が続いている。 [...]
全て見る
Equipments 特集
Amazon.co.jp(アマゾン)は4日、「Amazonお酒ストア」内の「Amazonワインストア」において、 専門家がワインを選んでくれる新サービス「Amazonソムリエ」の提供を開始した。 [...]
全て見る